今日から、少し「Ohm Studio」を利用した感じについて話を掲載したい。このOhm Studioとは一部では既に話題になっているクラウド用DAWで、サーバーを通じて世界中の様々な人達とコラボをすることができる次世代のDAWと呼べるサービス。以前に書いた記事
(Ohm Studioに関しては、『開発者に訊く、Ohm Force「Ohm Studio」 〜 “クラウドDAW”が実現する新しい形のコラボレーション 〜』も参照)
マルチトラックDAWなので、例えばある人はドラムトラックだけを打ち込み、別の人はベースを…という具合に、様々な人達が1つのプロジェクトに参加して録音なのに、まるでセッションのように楽曲を作っていくことができる。外国など遠隔地の人とコラボして音楽を作り上げることこそOhm Studioの醍醐味だと思う。(もちろん、プロジェクトに誰でも出入り自由にするほか、制限したり、非公開にするなどもできるが)
ソフトウエアは基本的に無料で配布され、コラボレーションなどOhm Studioならではの機能を利用する場合には月額課金されることで収益を得るというイマドキなビジネス。現在はまだβ版段階ですべて無料で利用可能だが、今年の早い段階で有料に移行するという。ちなみにβ版ユーザーには事前申込割引として6ヶ月で$44もしくはずっと利用できるLifetimeというプランが$252で提供されている。
個人的には、こうしたクラウドを利用したDAWとか音楽制作は今後スゴく活発になると思っており、Ohm Studioで楽しんでいきたい。なので、少し腰をすえて、複数のエントリーで現在のOhm Studioについて説明しようと思う次第。本日は、まず基本的なOhm StudioのDAW機能について。

Ohm Studioアプリでログイン後に表示される画面。左側がOhm Studioユーザーとコミュニケーションするチャット部、右側がDAWのプロジェクト管理部
アプリのダウンロードやメンバー登録などを終え、Ohm Studioアプリでログインすると、上図のような画面が表示される。画面の左側はOhm Studioユーザーとのチャットができる部分…これだけで普通のDAWとは違う。一方画面右側は音楽プロジェクトの管理部分。ここで自分のプロジェクトの設定をしたり、コラボ参加をする他ユーザーが作ったプロジェクトの閲覧や検索などもできる。
今回はまずOhm Studioの基本的な機能を理解するために、自分専用のプロジェクトを作り、ひと通りOhm Studioではどんなコトができるのか勉強することにした。

プロジェクト部分でNew Projectをクリックして新しい自分のプロジェクトを作成できる。プロジェクト名(曲名)の他、公開範囲やジャンル、雰囲気、説明などのプロジェクトに関する情報も入れる。
まずは、New Projectをクリックして新規プロジェクトを作成し、プロジェクト名の他に公開・非公開やジャンル、説明などのプロジェクトに関する情報を入れる。様々な人に来てもらうコラボレーション用プロジェクトの場合には、そうした情報をちゃんと入れておく必要があるのだと思う。今回はPrivateモードで小手調べなのでかなり適当(汗)。

Ohm StudioのDAW画面。他のアプリと際立って違うのは左下のプロジェクト参加者とのチャット機能があることだろうか(非表示にもできる)
作成したばかりのまっさらな新規プロジェクトを開いた状態の画面。最初はマスターのみがあるので、画面に1つだけチャンネルが表示されている状態。これにMIDIやオーディオのトラックを追加していって、音を作っていく。
ちなみに画面左下にはチャットが設けられ、プロジェクトに参加している人達だけのチャットを行うことも可能。便利に使えそうな気もするが、現在は日本語の扱いはあまりよくない様子。

MIDIトラックやオーディオトラックはpluginリストからドラッグ&ドロップしてラックを組み立てて作る。1つのラックが1トラックに相当する。
まず最初にMIDIのトラックを作成して…と考えたが、方法がちょっとわからず…「?」となった。実はMIDIトラックを作る場合には、プラグイン一覧のリストから楽器プラグイン(VST)をModular画面にドラッグ&ドロップして作るようだ。上図はソフト音源とエフェクターを組み合わせて「ラック」を作っている様子。このラック1つ1つがトラックになる。(ちなみに、わかりにくいが、Mixer画面でドラッグ&ドロップしても同じようにMIDIトラックを作ったり、エフェクトのインサートも可能。)

標準でGFORCEのOddity (Arp Odysseyをエミュレート)や、Minimonsta(MiniMoogをエミュレート)といったソフト音源が付属
標準で用意されている音源として特筆すべきなのは、GFORCE製のArp OdysseyをエミュレートするOddityやMinimoog音源のMinimonstaなどが最初から入っていること! そうした市販のモノが無料で使えると思うと得した気分になる。

Ohm StudioではサードパーティーのVSTiも利用可能で、手持ちの音源を気軽に利用可能。この図ではArturia Wurlitzer Vや、Native InstrumentsのAbbeyRoad Studio 60s Drummerを利用している様子。
一方、手持ちのVST音源も認識される。Logic Pro用に使っていた各種プラグインもちゃんとリスト内で表示され、問題なく動作したのにちょっとホッとした。
実は、Omni Forceの標準内蔵音源はかなり偏っていて(汗)、前にのべたようにArpのシンセのようなマニアックなモノが標準で用意されているのに、ドラム音源やピアノ音源など市販DAWには(実際に使えるかどうかの議論は別にして)間違いなく標準で入っていると普通は思うモノが無かったりする。なので、既に音源をひと通り揃えていてDAW標準音源は使わないという経験者はOKだけど、そうでない場合にはかなり面食らうことになる。

Ohm Studioでは開発元Ohm Force製の市販エフェクターなどが入っている。一方でReverbなどの基本的なエフェクターが欠落していたりも(笑)
標準搭載のエフェクターに関しても、内蔵音源同様のことが言える。Ohm Studio開発元Ohm Force社製のディストーションエフェクトOhmicideなど高品質でマニアックな市販エフェクトが提供されている一方で、Reverbなどの当然あるだろうと思うエフェクトが無い。現段階でOhm Studioに手を出すようなユーザー層はそれなりのエフェクタープラグインを既に所有しているという、スゴい割り切りなのだろうか。
Ohm Studio Webのフォーラムでは、そうしたプラグインを持っていない場合には今のところ「AmbienceなどのフリーVSTプラグインを使ってほしい」と書かれている。尚、最終的にはReverbなども用意される予定ではあるらしい。

プロジェクトを制作している様子。この辺りは基本的なDAWとそれほど変わらない手順で作業ができる。
DAWとしては、用意されているプラグインにかなり偏りがあるなど(苦笑)、DTMに慣れていない人には環境構築という面でハードルの高いOhm Studioではある。とは言え、そこそこの環境を持っている場合のセカンドDTMとしては悪くない。多少遊んでみると、それっぽく1曲のデータを作れた。

MIDIトラックのエディタアイコンをクリックして拡大表示することでMIDI編集画面に切り替わる。用意されているMIDI編集機能はベーシックなものにとどまる。
ちょっと良い点としては、MIDIのトラックで拡大ボタンを押すと、その部分が拡大表示でき、基本的なMIDIのエディットができるようになる。もちろんLogic Proなどを使っている身からすると、「ヒューマナイズ」機能は?とか「ベロシティリミッター」は?と思ってしまうのだけど、そのあたりは割り切りで。

オーディオトラックを拡大した状態。こちらもやはりベーシックな編集機能が用意されている。
オーディオトラックにしても、同様な感じ。Core Audio対応のオーディオ・インターフェースで録音でき(僕はTASCAM iU2を使用)、後はかなりベーシックなオーディオ編集があるのみ。
上記のMIDIやオーディオ操作にそれなりの編集が必要な場合、Logic Proなど他のDAWであらかじめ編集してしまい、それをオーディオファイル化したモノをOhm Studioに持ち込むというのが現実的な解かもしれない。

Webで公開するよう設定していれば、Webブラウザで誰でも(Ohm Studioユーザーでなくても)聞くことができる。
作成し終わったら、すぐにOhm StudioのWebサイトで公開状態になる…ということも面白い。普通なら、ミックスしてそれをSoundCloudに投稿…という手順を取るのだけど、そうした公開は極めてスムーズ。またプロジェクトの途中でも公開していれば、他ユーザーが聞くことが出来る。良い感じのプロジェクトを見つけたら、参加するといったこともできるようになる(プロジェクトのコラボに関しては次回)。

もちろん、Export機能を使ってプロジェクトをWAV等のオーディオファイルに書き出すことができる。
もちろんそこそこちゃんと仕上がるまでOhm Studio Webで公開しないように設定することもできるし、音をExportしてWAVなどで保存できる。こんか感じで本当にひと通りのOhm StudioのDAW機能について見てきた。次回には、Ohm Studioの一番の「売り」である、多くの人達がOhm Studioを使い、ネットでコラボレーションして楽曲を作り上げるコトについてエントリーを書きたいと思う。



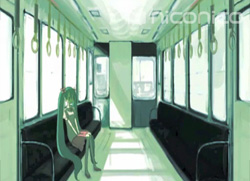












[…] […]
[…] 現在は日本代理店は無く、海外の開発元サイトからDL販売に。価格は£99.99(記事記載時点で約12,000円)。ちなみにクラウドベースのDAW「Ohm Studio」には最初からこのThe OddityなどのGForce社音源が最初から含まれていたりする。(Ohm Studio参考記事) […]